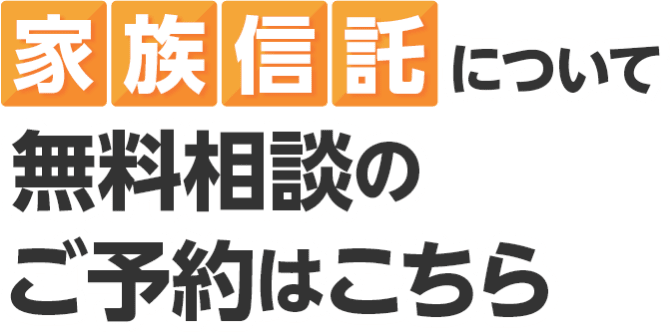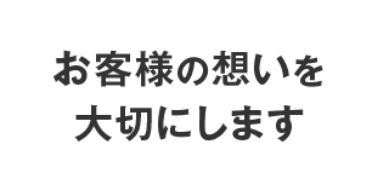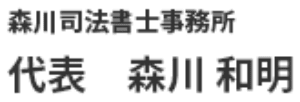-
【町田市】認知症の妻を守りつつ全財産を息子に譲りたいという悩みを家族信託で解決
Q:認知症の配偶者をもつ(町田市)Kさんからのご相談例 私には認知症の妻と、一人娘がいます。私より5才年上の妻は、80になる前から物忘れが多くなり、気づいたころには認知症を発症しており会話すら難しいほど進行していました。お風呂の介護など自宅で生活を続けるのが負担に感じた頃に、受け入れてくれる施設が見つかったため、今は施設で生活しています。 娘は私たち夫婦と一緒に住んでおり、家事の得意ではない私の代わりに仕事をしながらも家事全般を担ってくれているのでとても助かっています。母親の認知症が出始めたころも、進んで介護を手伝ってくれ、母親が施設に入った今でも休みのたびに施設に顔を出し、話し相手になったり細々とした用事をこなしてくれています。今のまま、父娘ふたりで生活を続けていければ良いのですが、私ももうすぐ妻が認知症を発症した80になります。認知症の進行の速さを目の当たりにしたこともあり、もし私も認知症になってしまったら優しい娘にさらに世話をかけることになるのではないか、施設に入所している妻や同居している娘の生活はどうなってしまうのかなど、これから先のことを考えるといろいろ心配でなりません。 私の所有する財産といえば、自宅と預貯金が少しある程度です。今の妻の状態では、資産を管理するのは難しいので、娘にすべての財産を譲りたいと考えています。その財産で妻の施設での生活の援助や、娘の生活の手助けができれば、これからの生活に対して少しは安心した気持ちで向き合えるのではないかと思っています。 私にもしものことがあったとき、せめて金銭面だけでも負担をかけないように贈与など良い方法がありましたら教えてください。 A:家族信託による配偶者認知症の対策 現在の社会では、65歳以上の5.4人に一人は認知症であるといわれています。 今後も高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数はさらに増えることは間違いありません。 団塊の世代が75歳以上になる2025年には認知症患者数は700万人前後に達するだろうと、厚労省も発表しているように、認知症は誰もがいつ発症してもおかしくはない時代なのです。 ですから、奥様の介護をされていたKさんがご自身の認知症について心配されるのは当然のことだと思います。 いざというときに、娘さんを困らせることがないように、Kさんが元気なうちに娘さんに負担をかけないように準備をすることはとても大切なことです。 認知症になり判断能力の低下が確認されると、資産管理は難しいと銀行などで判定され、誤って想定外の資産運用ができないように資産は凍結されます。 凍結された資産は、資産の名義人以外は利用することができないため、Kさんの場合では娘さんが代わりにということができません。 そうなると、Kさんの通院費や施設に入所する際の入所費用、すでに施設に入っている奥様の援助などを、娘さんがKさんの資産を活用して代わりに支えていくことができず、金銭面で大きな負担を強いることになりかねません。 そこで、活用したい方法は「家族信託」です。 この家族信託というものは、認知症などで財産の管理ができなくなった場合に備えて、信頼できる家族に自分の財産を預けて代わりに管理や処分をしてもらえるように権限を与えておく方法です。 家族に財産を託すので、基本的に高額な報酬などが発生しないのがおすすめする理由でもあります。 大きな富を持つ資産家だけでなく、誰でも気軽に利用できるため、近年利用者が増加している信託契約です。 家族信託には3つの役割を持つ登場人物がいます。 まず一人目は、信託を依頼する依頼者=委託者です。 財産の持ち主で、これから財産の管理や処分を誰かに任せたいと考えている人で、今回はKさんが委託者です。 二人目の登場人物は、受託者=託された財産を管理したり処分したりする人で、委託者の信頼する家族です。今回は娘さんが受託者となります。 そして三人目は、信託された財産から生じた利益、マンションの賃料や売却費などがそれにあたります。この利益を受け取る人=受益者です。 まず、Kさんが元気な間はKさんが受益者となり、貯金などを生活費に利用したり、奥様への援助に利用します。 Kさんが亡くなったりした場合は、奥様が次の受益者になるよう設定することも大切です。 これで、もしKさんが認知症を発症して判断能力の低下があり銀行などの資産が凍結されそうになったとしても、娘さんがKさんの資産を活用してKさんの生活を支えたり、奥様を援助することができます。 資産をどのように使って良いか、どのタイミングで自宅を売却するかなど、Kさんの希望を家族信託に盛り込むことで、より柔軟な相続の形をとることができるのもおすすめしたいポイントです。 家族信託のデメリットの一つとして、認知症を発症してしまうと、判断能力の低下や喪失の可能性があるとしてあらゆる契約ができなくなってしまうことです。 つまり、元気なうちしかできない制度なので、注意が必要です。 この仕組みを活用することによって、親が認知症になった場合でも財産の管理がスムーズに行われるので、受託者である娘さんに金銭的負担をかけることなく、日々を過ごしていけるでしょう。 娘さんとも相談の上、デメリットも考慮し元気なうちに、家族みんなが安心して生活していけるように準備しておきましょう。
-
【相模原市】介護や入所費などの費用負担を家族信託で解決
Q:父の資産運用と介護負担について(相模原市)Oさんからのご相談例 年をとった父のこれからについて相談させてください。 わたしは神奈川県に生まれ、首都圏に本社のある企業に就職しましたが大阪支社に転属になってからそちらに居を構え、もうすぐ定年をむかえます。 相模原にある実家には年老いた父がひとりで暮らしており、町田に住む弟がちょこちょこ顔を出して、なにか手が必要なときには手伝ったりしているようです。 先日、弟から連絡があり、父の物忘れが増えたので心配だと相談されました。 足腰元気な父は、何年か前に母を亡くしてからもひとりで自由きままに生活していたのですが、玄関の鍵を締め忘れたり、うっかりコンロの火をつけたままにしてしまうことがあるようです。 まだ認知症というほどの状態ではないのですが、なにかあってからでは遅いですし、弟家族が一緒に住もうと話しているが父が実家を手放したがらないという話でした。 父は、施設に入所しなければいけなくなったときは、実家を処分して売却費をあてることは認めているそうです。 わたしは神奈川を離れてもう何年にもなりますし、盆正月にたまに帰る程度です。家族も大阪から離れたくないようなので、このまま弟にお願いするつもりですが、代わりに資金を援助しようにももうすぐ定年のためその後の生活が安定するかわからないのでなかなか言い出せない状態です。 父の面倒を自分がみることは出来ないので、 その代わりといってはなんですが、自分は父の財産を相続しないで構わないので 父の資産の管理を弟に任せて、最後は弟に相続してもらう良い方法はありませんか? A:家族信託で介護などの費用負担を解消 家族信託とは、家族による家族のための財産管理の手法で、保有する不動産や預貯金などの資産を、信頼できる家族に託して、その管理や処分などを任せる仕組みです。 家族や親族に管理を託すので、第三者に託すより安心して託すことができます。また、家族や親族に託すメリットは他にも、高額な報酬が発生しないという点もあります。 そのため、資産家ではなくても、誰でも気軽に利用しやすい仕組みと言えるでしょう。 また、負担や制約の多い成年後見制度のように毎年家裁へ報告する義務はありません。 元気なうちに資産の管理や処分を託すことによって、元気なうちは自分の指示に基づく財産の管理を行い、万が一、認知症などによって判断能力が低下がみられた場合は、託した家族によって信託契約に指示した通りに財産管理を実行してもらうことができます。 また、資産の運用や不動産の売却や建築なども、託された家族の責任と判断で可能となるので、滞ることなくスムーズに運営することができます。 今回の場合では、お父さまは実家を手放したくないが、認知症などで住めなくなった場合は売っても良いと考えていらっしゃるとのことでした。 ですから、お父さまの預貯金とご実家を信託財産として、弟さんと家族信託を組むことをおすすめします。 依頼される委託者はお父さまで、信託財産を管理する受託者を弟さんとします。 お父さまが御元気なうちは預貯金などをお父さまの自由に使っていただいて、万が一のときは弟さんが管理します。 ご実家を売却するタイミングはお父さまとご相談なさったうえで指定しておきましょう。 例えば、認知症などで判断能力の低下がみられ、お父さまが施設に入所しなければいけなくなった場合や、介護や通院費など預貯金では賄いきれなくなった場合など、条件を指定することでお父さまのご希望に沿った資産管理ができます。 お父さまが亡くなった場合の信託財産の帰属先を弟さんに指定しておき、弟さんがお父さまの介護をしていただいた苦労に報いるかたちを作っておきましょう。 相続のかたちは家族ごとにそれぞれ違い、いろいろなかたちがあります。 介護などの負担は費用の面だけではありませんが、費用が大きな負担になることは間違いありません。 費用の心配なくお世話や介護ができると、心のモチベーションにも繋がり良い家族関係を続けることにも繋がります。 家族みんなが元気なうちに話し合って、より良い相続のかたちを見つけてください。
-
【町田市】こどもたちに共同で不動産の管理を任せたい悩みを家族信託で解決
Q:高齢になったご主人の所有する不動産の管理を子供に任せたい(町田市)Jさんからのご相談例 主人は資産家で、マンション1棟と自宅を兼ねた商業施設の入ったビルを所有しています。主人は80代になってから物忘れが多くなってきたように思えるので、夫婦で相談してできれば早いうちに相続対策を行いたいと考えています。 基本的に主人が所有しているすべての不動産を管理していて、税金などの支払いも主人が行っているのですが、主人が動けなくなった場合を考えると心配です。 わたしが手伝うことも検討したのですが、わたし自身も高齢なので健康面に不安もあるので、できればこどもたちに託したいと思っています。 わたしたち夫婦には、子供が二人おりまして、姉である長女はまだ結婚しておらず、主人の所有しているマンションの一室を借りて住んでいます。 弟の長男は、結婚していて同じ町田市に戸建てを購入し、孫とともに暮らしています。 管理修繕や税金の支払いなどの管理を、どちらかひとりに任せるには負担が大きいと思うので、しばらくは姉弟ふたりで協力して管理をしてもらえるかたちが理想です。 共有で相続する場合に気をつけるべきことなど、なにかありますか。 身内だけで全部の手続きが済むようなら、できればそうしたいです。 A:家族信託で効率よく不動産を相続する まず、ご主人が遺言を使うかたちでの相続について解説していきます。 遺言は、亡くなってからの相続について記すものなので、ご主人がご存命の今、所有している不動産の管理を託すことには使えません。 遺言とは「わたしが死んだあとは、誰々にこれを譲る」と指定するものです。 信託を利用することなく遺言書を作成するだけだと、配偶者であるJさんにすべての財産を相続させることなどは可能ですが、Jさんが亡くなったあとのことを指定するためには、Jさんが遺言書を作成し資産の分割方法と相続先を指定しなければいけません。Jさんが遺言書を残さなかった場合は長女と長男で話し合って財産の分与を行うことになります。 また、ご主人が認知症などで判断能力の低下を診断された場合だと、後見人がすべての不動産を管理することとなるので、長女と長男のふたりで共同管理することは基本的にできず、施設入所などでお金が必要になったときにマンションなどを売却するにも、家庭裁判所の許可が必要となるなど、簡単に資産管理することができません。 また、不動産の管理に慣れることを目的として子どもたちに共同で管理を任せたいと考えていらっしゃるとのことですが、共同で管理を行うことは可能ですが推奨できません。 資産の売却や管理などの運営を行う際、共同管理者の相互の意思疎通や連携が必要となります。その運用に重要な意思決定や迅速な対応に迫られた場合、なんらかのトラブルに発展しかねません。 また共同で管理すると、誰かひとりの債務も連帯責任として共同で追うことになるなど、デメリットが多いからです。 ですから、共同で管理をするのではなく、資産をそれぞれに託したり、どちらかに託して、もう一人に監督してもらうなどの方法が良いでしょう。 弊所からの提案 Jさんご夫婦が希望される相続方法を実現するためには、家族信託を活用するのが良いでしょう。 今回は、長女がマンション、長男がご自宅兼用商業施設の入ったビルを管理するという2つの信託契約を結ぶことを提案しました。 まず、信託する財産はマンション、自宅兼用商業施設の入ったビル及び現金です。 信託を依頼するのはご主人さまで、不動産の収益は生活するのに必要ということで、そのままご主人が受け取り、ご主人が亡くなったあとはJさんが受け取れるようにします。 以上の内容から、信託契約の構成はこのようなかたちになります。 契約1 【信託財産】マンション、現金 【委託者】ご主人 【受託者】長女 【受益者】ご主人→Jさん→長女 契約2 【信託財産】自宅兼用商業施設の入ったビル、現金 【委託者】ご主人 【受託者】長男 【受益者】ご主人→Jさん→長男 ご主人が不動産管理の相談が受けられるうちは、姉弟にそれぞれ管理してもらって、ご主人が監督しながら収益を受け取ります。 共同で管理した場合、双方の合意がないと手続きをすすめることができないのですが、それぞれで管理するので経験のあるご主人が協力することで運営を学び、最終的には子どもだけでも管理できるようにするのが目的です。 受益者ですが、第一受益者であるご主人が亡くなったあとのJさんの生活を保障するために、第二受益者をJさんに設定すると良いでしょう。 Jさんが認知症などを発症した場合でも、お子さんたちが代わりに不動産収益を使ってスムーズに対応することができます。 Jさんご夫婦が施設に入所することになったときは、自宅ビルかマンションを売却して入所資金にあてるなど、どのような場合にはどのような資産をあてるかなど、事前に話し合って余計なトラブルを回避するのが良いでしょう。 あと、Jさんが亡くなったあとですが、その時点で信託契約は終結し、それぞれが託された資産の収益を受け取ることになります。 老朽化による建て替えや大規模修繕が必要となった場合、共同管理者の意見が合わないと手続きが行えずトラブルになるという可能性もなく、各自の意思決定で管理を行うことができます。 もし、ご主人の体調面などが心配だと思われるなら、受託者の管理役として「信託監督人」や「受益者代理人」などに姉弟を設定するという方法もあります。 「信託監督人=受託者の財産管理方法などを監視監督するひと」や「受益者代理人=信託契約の変更や受託者の解任などの受益者が有している管理者的な役割を代行するひと」は、本来受益者の監督役であり、信託契約で設定することができるものです。 姉弟のそれぞれの信託契約に、互いがその役割につくことで、受託者の管理だけではなく相談役として協力することが可能となります。 困ったとき助け合える関係を作ることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。 Jさんご夫婦で相談して相続のかたちを決めることによって、お子さまたちも納得して不動産の管理などの相続手続きに協力することができます。 ご家族で協力して資産を守っていけるよう、しっかりとした相続計画をたてることが家族の幸せを守ることにも繋がっていきます。
-
【町田市】合意した遺産分配を家族信託で明確にしたい
Q:父の望む遺産の分け方をきちんとしたかたちにしたい(町田市)Iさんからのご相談例 先日、母の三回忌に家族みんなが集まる機会がありました。そのとき、父より財産の分配について家族でしっかり話し合っておきたいという提案がありました。 父は以前脳溢血で倒れた際、半身に麻痺が残ってしまったため、日常生活のお手伝いが必要となりました。 母が亡くなってからは、近くに住んでいたわたしの妹夫婦が同居してくれています。 日頃から妹に負担をかけているし介護費用もかかることもあるので、父としては妹に多く遺産を残したいという話でした。 長男であるわたしは、仕事の関係で海外に赴任することが多く、父のことを妹に任せたままになってしまっていることを心苦しく思っていたこともあるので、父の望む通りのかたちで相続をまとめたいと考えています。 父の資産は、自宅を含む不動産が二軒と預貯金になります。 わたしとしては遺産放棄でも良いのですが、父としてはなんらかのものは残したいと思っているようで、自宅と預貯金を妹に、不動産の1軒をわたしに相続してもらいたいそうです。 妹夫婦も父の望むようにすればいいと言っているので、父が元気な今のうちにきちんとしたかたちにしておきたいと思っています。 どのようなかたちにすればいいのか、なんらかの問題がないのかなど知りたいです。 A:家族信託による生前に行う遺産分割の方法 日頃、介助などで世話になっている娘に多く資産を残したいというお父様の希望を、お父様のお元気なうちにかたちにしたいという息子さん。 仲の良い家族がみんなで相談して決めた相続のかたちをしっかりしたものにするための手続きとして 家族信託をおすすめします。 遺言ではなく、推定相続人(この場合ですと長男のIさんと、妹さん)が合意したものを文書にしただけでは法律上で無効となります。 お父様に、家族みんなが合意した内容を記した遺言書を作成してもらうことで、相続のかたちを作ることもできますが、遺言はいつでも書き換えたり撤回することができてしまうので、きちんと確定したというかたちにはできません。 ですから、信託契約を活用して、生前の遺産分割協議を友好的に確定しましょう。 それでは、家族信託の内容を整理しましょう。 まず、信託するお父様の資産について。 お父様の資産は①ご自宅②不動産(現在は管理会社に管理を委託し、収益をお父様が受け取っている状態)③預貯金とします。 ①ご自宅と③預貯金は妹さんに、②不動産は息子のIさんに継いでもらいたいとお父様が希望されており、妹さんもIさんも了承されているので、それぞれをお父様と信託契約を結びましょう。 それでは、お父様と息子のIさんとの家族信託について説明します。 委託者をお父様、受託者が息子のIさんとし、受益者はお父様として信託契約を締結します。 信託する財産は②不動産です。 これで、お父様が元気な間は②不動産の収益はお父様が今までとおり受け取ることができ、万が一、お父様が認知症などで判断能力が低下した場合、管理を任せている不動産への手続きをIさんが代用することができるので、管理会社との提携更新や売却などの手続きをIさんの判断で行うことができ、その収益をお父様のために使うことができます。 Iさんの名義になっている②不動産については、、お父様が亡くなった時に終了しⅠさんに財産が帰属する内容を入れることで、収益を受け取る権利もIさんのものとなります。 続いて、お父様と妹さんとの家族信託の場合は、 委託者をお父様、受託者を妹さん、 受益者はお父様、信託財産は①ご自宅③預貯金です。 Iさんと同じように信託契約は、お父様が亡くなった時に終了し、残った財産は妹さんに帰属する内容も付け加えます。 ご自宅や預貯金はこれまで通り、お父様が使うことができますし、もしお父様が入院したり認知症を発症したとしても、生活費や入院費などの支払いを、妹さんが委託された財産を管理して支払ってもらうことができるので、妹さんに金銭的負担をかけることなく安心して生活していくことができます。 残った財産は妹さんが相続するので、日頃介助などで世話になっている娘さんに、息子さんより多くの資産を譲ることができます。 また、それぞれの信託契約に「内容の変更はできない」という旨を定めておくことも重要です。 この家族信託は、生前の財産管理機能と遺言の代替機能を備えた内容となっており、家族の合意のもとに決めた内容を誰かひとりの判断で変更もできなくなっているので、将来の遺産分割内容を確定する効果もあります。 きちんとしたかたちにすることで、お父様も安心して生活することができ、妹さんも不安なく介護でき、Iさんも家族を気にすることなく海外でのお仕事を邁進することができるのではないでしょうか。 合意のあいだにしっかりとしたかたちを整え、家族信託を活用して、仲良く家族で暮らしていける環境を作っておきましょう。
解決事例
認知症対策生前対策相模原・町田